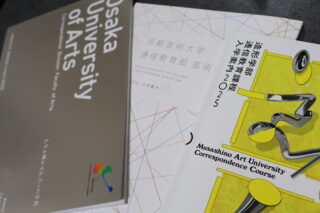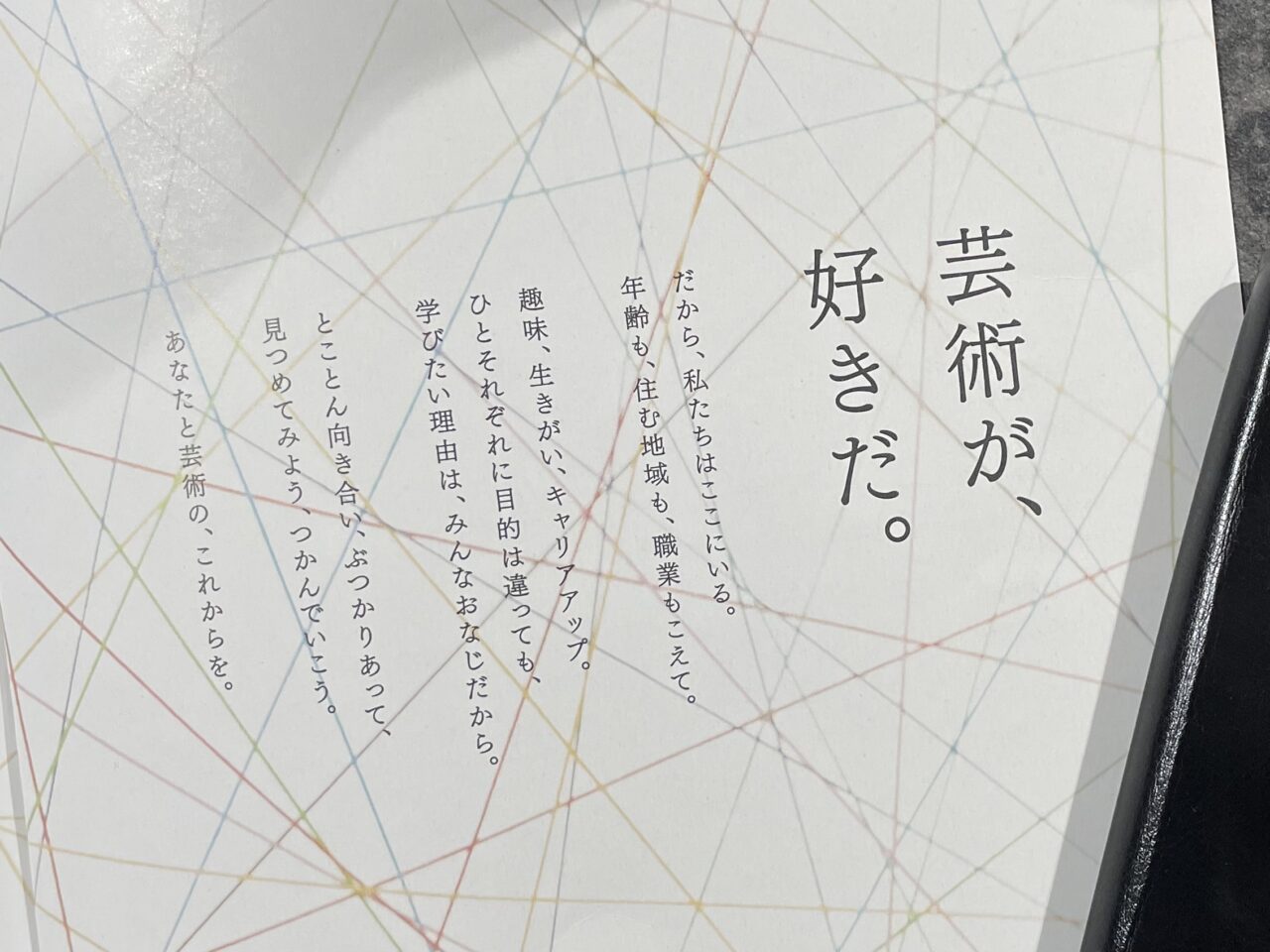
自分は四国に住んでいます。車で本州に上陸するためには、橋を渡るために往復分の通行料を毎回お支払いしています。
関東、関西、その近辺に住んでいたら、スクーリングで大学に行くというのも、もう少し気軽なことなのかもしれません。でも地方にいると、それが一気に“旅”の規模になります。交通費、宿泊費、そして移動にかかる時間。そのすべてが「学びたい」という気持ちより先に、現実として立ちはだかります。
なので、「通信で学ぶ」という選択肢の中でも、京都芸術大学の「全科目(※陶芸コースを除く)オンライン卒業可という情報は、かなり惹かれる部分になります。スクーリングのために県外へ出る必要がなく、授業も課題提出もすべてオンラインで完結する。
実際どこまで“美術の学び”として成立するのか、そのあたりはまだ自分の中でも整理しきれていませんが、地方在住としては、かなり現実的で魅力的な選択肢のひとつだと思っています。京都芸術大学 通信教育部について情報をまとめていきます。
学びの形が変わる ― 完全オンライン化の意義
京都芸術大学 通信教育部では、2025年度から全科目(※美術科陶芸コースを除く)のフルオンライン化が発表されています。つまり、スクーリング(対面授業)のためにキャンパスへ通う必要がなくなり、自宅で全ての課程を修了できる という新しい学びの形です。
通信制の美大といえば、これまでは「レポート+年数回のスクーリング」が基本でした。作品の講評や造形実習など、どうしても対面でしか成り立たない部分があると思われてきたからです。けれど今は、映像教材・オンライン講評・デジタルポートフォリオ提出といった仕組みが整い、それぞれの「制作プロセス」や「表現意図」をオンライン上で共有できる時代になりました。
もちろん、直接キャンパスで学ぶ経験には、オンラインでは得られない価値があると思います。ただ、物理的な距離や時間の制約を理由に学びを諦めなくていいというのは、地方在住の方にとっては、ものすごく現実的でありがたい変化です。
通学がなくなるということは、移動や宿泊にかかる費用と時間を、すべて制作や学びに充てられるということでもあります。そのぶん、自分のペースでじっくり作品に向き合い、考えを掘り下げる余白が増える。通信制という仕組みが、単なる「代替手段」ではなく、新しい学びのかたちとして進化しているだと感じます。
カリキュラムと学べる分野と学費について
京都芸術大学の通信教育部には、芸術教養学科をはじめとする複数の学科・コースがあります。美術・デザイン・写真・映像・文芸など、扱う分野は幅広く、在籍している年齢層も幅広く、10代の新卒から、90代の学び直しの方まで。
学べる学科と費用など、以下にまとめました。
※この記事は、2026年度入学向け(2025年度時点)の情報を参考にしています。
文化コンテンツ創造学科
アート、デザイン、文章、音楽、食などを横断しながら、文化を“つくる人”としての発想を磨く。創造を「個人の表現」にとどめず、社会と共有する力を育てる学びです。
- 音楽コース(2026年度 新設コース)
楽器を弾いたことがなくても、楽譜が読めなくても始められる。DTM(※デスクトップミュージック:PCを使用して音楽を制作する手法)を通して、テクノロジーを使用した音楽制作の技術と発想力をいちから実践的に習得できる。 - イラストレーションコース
現役のクリエイターによる授業を通して、基礎から応用技術まで幅広く学べる。また「pixiv」を運営するピクシブ株式会社と共同開発したオリジナル教材を使うというのも印象的。 - 映像コース
スマートフォンやPCだけで映画、ドラマ、MV、SNS動画、アニメーションなど多様な映像ジャンルを学べるコース。専門機材なしでも基礎から企画・撮影・編集・発信までを体系的に習得できます。 - グラフィックデザインコース
ポスターやパッケージなど、視覚的に「伝える」デザインを学ぶ。コンセプト設計からレイアウト、タイポグラフィまで、表現と機能の両立を探る内容です。Adobe系ソフトの操作を通して、実践的なデザインスキルも磨きます。 - 書画コース
書や水墨画といった“伝統的な表現”を、通信という形式で学べるコース。筆・墨・紙といった素材の扱いから、表現の構造を理解しながら、手を動かすことで「書く/描く」ことの思考を深めていきます。 - 食文化デザインコース
「食」を単なる消費ではなく、文化や表現として捉え直すコース。人や社会、地域との関わりを軸に、食を“つくる・伝える・感じる”という行為を多面的に学ぶ。「ライフデザイン」「ビジネスデザイン」「体験デザイン」という三つの視点から、食を通して暮らしや価値観を見つめ直していく内容です。 - 文芸コース
文章を通して「伝える力」を磨くコースです。小説やエッセイなど、形式にとらわれず、言葉を使って自分の世界をどう描くかを探ります。描写や構成の技術だけでなく、読者の心に届く“表現としての文章”を追求します。 - アートライティングコース
アートを「書く」ことで理解し、伝える力を育てるコースです。批評やエッセイ、展覧会レビューなど、言葉を通して作品と向き合う訓練を行います。文章力だけでなく、アートの背景を読み解き、自分の視点を言葉にする力を磨きます。
| 区分 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 入学時 | 入学選考料 | 20,000円 |
| 入学金 | 30,000円 | |
| ①音楽、イラストレーション、映像、グラフィック、書画、食文化デザインコース ②文芸、アートライティングコース | 授業料 | ①355,000円 ②348,000円 |
| 保険料 | 140円 | |
| 1年目合計 | ①405,140円 ②398,140円 |
| 卒業までの合計金額 | |
|---|---|
| 1年次入学(4年間) | ①1,470,140円 ②1,442,140円~ |
| 3年次編入学(2年間) | ①760,140円 ②746,140円~ |
スクーリング費用を含む
芸術教養学科
芸術・文化・デザインの意味を横断的に学ぶ総合教養系の学科。デザイン思考で未来を構想し、文化や伝統から過去を学ぶ—その両輪で創造的な教養を育てます。
- 芸術教養学科
社会の中でアートやデザイン、文化が果たす役割を幅広く学ぶコース。伝統行事や、食文化、美術、イベントのデザインなどを横断的に扱いながら、“暮らしの中に芸術を活かす方法”を探ります。
| 区分 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 入学時 | 入学選考料 | 20,000円 |
| 入学金 | 30,000円 | |
| 1年目 | 授業料 | 170,000円 |
| 保険料 | ※授業料に含む | |
| 1年目合計 | 220,000円 |
| 卒業までの合計金額 | |
|---|---|
| 1年次入学(4年間) | 730,000円 |
| 3年次編入学(2年間) | 390,000円 |
スクーリング費用を含む
芸術学科
芸術を「つくる」だけでなく、「考える」「伝える」ことまでを含めて探究する学科。表現の背景にある思想や文化を理解し、作品を“ことば”でも伝えられるようになることを目指します。
- 芸術学コース
芸術の背景にある思想や美学を探りながら、「表現をどう言葉にするか」を考える。批評や研究を通して、つくる側・受け取る側の両方の視点を身につけます。 - 歴史遺産コース
古文書、掛け軸、仏像、伝統建築といった「文化遺産=“ほんもの”」に触れながら、美術史・文化財保存・調査方法を体系的に学びます。
実践的には、史料の読み解き、素材や構造の分析、修理技法の演習も取り入れられており、「過去から現在までをつなぎ、文化を記録・継承する」という視点が育まれるコースです。 - 和の伝統文化コース
茶道・華道・書道・装束など、日本の伝統文化を学び、現代とのつながりを探る。形式ではなく、そこにある思想や所作の美を理解する学びです。
| 区分 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 入学時 | 入学選考料 | 20,000円 |
| 入学金 | 30,000円 | |
| 1年目 | 授業料 | 231,000円 |
| 保険料 | 140円 | |
| 1年目合計 | 281,140円 |
| 卒業までの合計金額 | |
|---|---|
| 1年次入学(4年間) | 1,070,140円 ~ 1,274,140円 |
| 3年次編入学(2年間) | 608,140円 ~ 752,140円 |
スクーリング費用を含む
美術科
日本画、洋画、染織、陶芸など、素材や技法と向き合う実技中心のコース。基礎から制作までを通して、自分の中の「表現の軸」を見つめ直します。
- 日本画コース
彩色・箔・岩絵具など日本画独特の画材と技法を、基礎から学べるコース。古典作品を観察し模写することで「技術を読む力」を養い、同時に自分自身の表現を探るプロセスも重視されます。
美術の伝統を身体で捉え直しながら、“自分なりの日本画”に向き合っていく学びです。 - 洋画コース
デッサンやドローイング、油彩やアクリルなど、多様な画材を使いながら造形表現が学べます。対象を観察し、形や色を構成する力を養い、立体制作やコラージュなど複数の素材・技法に触れて“絵画の領域を自分なりに広げる”ことを目指します。
観察から自由制作へ。画面構成の魅力を掴み、自分の表現を探求します。 - 陶芸コース
器からインテリアやオブジェまで、土と火と向き合いながら学ぶコース。ろくろ・石膏型・手びねり・タタラといった成形技法、上絵や釉薬の加飾技法も学び、土の声や焼成の表情に耳を傾ける時間があります。
初心者からでも始めやすい造形課題から、窯焚きや専門知識までを段階的に学んでいける構成です。 - 染織コース
布を通して「人を、そして自分を」知るという視点が印象的なコースです。「染」と「織」という技法を軸に、身にまとい、住まいとして、祈りとして使われてきた布の構造やその変遷を丁寧にたどります。
素材や技法を学ぶだけでなく、「なぜ布を選び、なぜ技を使うのか」という問いを作品制作を通して掘り下げていく時間も設けられています。 - 写真コース
実践的な技術とともに「写真を通して思考する力」を育てる場です。デジタル撮影の基礎、構図・編集・フォトコラージュなどを学びながら、単なる“きれいな写真”を超えて、「何を見せたいのか」「どんな問いを残したいのか」を掘り下げます。
撮影、編集、発表までを通して、自分の視点を社会に届けるための表現を磨いていくコースです。
| 区分 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 入学時 | 入学選考料 | 20,000円 |
| 入学金 | 30,000円 | |
| 1年目 | 授業料 | 327,000円 |
| 保険料 | 140円 | |
| 1年目合計 | 377,140円 |
| 卒業までの合計金額 | |
|---|---|
| 1年次入学(4年間) | 1,646,140円 ~ 1,808,140円 |
| 3年次編入学(2年間) | 992,140円 ~ 1,064,140円 |
スクーリング費用を含む
環境デザイン学科
環境デザイン学科の3つのコースは、それぞれの分野に重なり合う部分も多いですが、扱うスケールや視点が少しずつ違うようです。建築は「構造としての空間」、ランドスケープは「自然と人の関係」、空間演出は「人が体験する場のデザイン」。どれも環境をつくる学びですが、見ている世界の広さや深さが異なります。
- 建築デザインコース
建築という大きなスケールの表現を、「設計」「模型」「スケッチ」「CG」などを手段にして学ぶコースです。身近な住まいや家具といった小さなスケールから、公共空間や都市の構造という大きなスケールまで、視点を行き来しながら「環境をつくる」ことの意味を探っていきます。
未経験でも、図面や模型という言葉や形に触れるところから始められる設計実習的なステップが用意されているため、「建築」をこれから学びたい人にも開かれたコースです。 - ランドスケープデザインコース
自然・都市・地域と人との関係をデザインする学びの場。日本庭園・都市緑地・里山まで、風景を「つくる」「保つ」「編集する」といったプロセスを通じて考えていきます。
専門家による講義・実習、図面や模型制作、植物や環境の知識といった多面的な技術が組まれており、初心者からでも段階的にステップを踏める設計です。 - 空間演出デザインコース
インテリアから雑貨、展示空間まで、生活の「場」をデザインする学び。模型や製図、プレゼンテーションなどの技術を学びながら、空間×ビジュアル×社会という視点を横断して「どう暮らしをデザインするか」を探っていきます。
| 区分 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 入学時 | 入学選考料 | 20,000円 |
| 入学金 | 30,000円 | |
| 1年目 | 授業料 | 327,000円 |
| 保険料 | 140円 | |
| 1年目合計 | 377,140円 |
| 卒業までの合計金額 | |
|---|---|
| 1年次入学(4年間) | 1,646,140円 ~ 1,808,140円 |
| 3年次編入学(2年間) | 992,140円 ~ 1,064,140円 |
スクーリング費用を含む
サポート体制と学習の進め方
京都芸術大学の通信教育は、完全オンラインでも学びを続けられるように細かく設計されおり、学習の流れやサポート体制はかなり丁寧なようです。
オンデマンド授業とライブ授業
まず授業のスタイルは、大きく分けて2種類あります。
オンデマンド授業とは、録画された授業を好きな時間に見る方式。スマホやパソコンからアクセスでき、何度でも見直せるので、自分のペースで学びを進められます。
もうひとつはライブ授業で、先生がリアルタイムで行うオンライン授業です。時間が決まっている分、他の学生と一緒に学べる臨場感があり、質問もその場でできます。学科によってどちらの形式が中心になるかは異なりますが、どちらも「社会人でも続けやすい設計」になっているのが特徴です。
学習システム「airU」
すべての授業は、大学独自のWebシステム「airU(エアユウ)」で管理されています。ここで授業動画の視聴、レポートの提出、成績確認、履修登録まで完結。
「今日は何をやればいいか」が一目でわかるようになっていて、忙しい人でも学習のリズムを作りやすい仕組みになっています。
学びを支える仕組み
通信制は一人で進める印象が強いですが、京都芸大では学生同士がつながる仕組みもあります。授業の掲示板やオンラインフォーラムを通して、意見交換や情報共有ができるようになっており、「同じように働きながら学ぶ仲間がいる」というのは心強いポイントです。
質問があれば、airU上の「コンシェルジュ」に問い合わせできるサポート窓口もあります。事務的な手続きから履修相談まで、メッセージで完結するため、通学とほぼ変わらない距離感でやりとりができます。
学びの進め方(例)
- 平日の夜や休日にオンデマンド授業を視聴
- 学んだ内容をもとにレポートや作品課題を作成
- airU上で提出し、数日〜数週間後に講評を受け取る
- 年に数回、オンラインまたは対面のスクーリング(実習授業)に参加
まとめると、京都芸術大学の通信教育は「自分の生活の中で、どれだけ学びを習慣化できるか」を支えてくれる設計です。完全オンラインでも、孤独にならないような“温度のある学び”ができる仕組みが整っていると感じます。
京都芸大・通信の口コミを調べてみる
どんなに気になる学校でも、実際に通っている人の声を聞いてみないとわからないことが多いですよね。
通信課程は通学より学費は抑えられますが、それでも時間とお金をかける大きな決断です。だからこそ、良い点も不満点も含めてリアルな声を知っておくことが大切。
ここでは、京都芸術大学 通信教育部の口コミをできるだけフラットにまとめてみました。
肯定的な評価
入学制度・受講方法について
— 在学生の口コミより“学びたい”という気持ちさえあれば入学できる大学です。特別な試験もなく、出願手続きを済ませれば誰でもスタートできます。10代から社会人、定年後に始めた方まで年齢層が広く、授業はZoom、課題はWebや郵送で提出できるので全国どこからでも学べます。
入学の門戸が広く、オンラインで完結する仕組みが整っている点は多くの学生に好評です。一方で、誰でも入学できる分、自分の目的意識や学ぶ姿勢が問われる環境でもあります。
学習環境・ペース・コミュニティ
自分のペースで学べるのが助かりました。仕事が忙しい時期は少しペースを落とし、オンラインのコミュニティで他の学生と相談したり、スクーリングで直接話したりして刺激をもらえました。
— 在学生、卒業生の口コミより卒業してみると、絵もかなり上達していて、“大学で学ぶって面白いな”と感じました。カリキュラムが段階的に組まれていて、無理なく基礎から積み上げられたのが良かったです。
仕事や家庭と両立しながら学べる柔軟な環境と、段階的に力をつけられるカリキュラムが評価されています。オンラインやスクーリングで学生同士の交流が生まれ、学ぶモチベーションにつながっているようです。
学費・学びの価値
— 在学生の口コミよりまったく知らなかった分野にも触れられて、正直、値段以上の価値を感じました。入学して半年ほどで“もう元は取れたな”と思えるくらい、学びの幅が広がりました。
新しい分野に触れながら学びを深められた点に満足しており、学費に対しても納得感があると感じる学生もいるようです。
厳しめの評価
Webシステム・履修管理について
— 学生の口コミより授業や履修登録などはすべてWeb上で完結するのですが、操作が分かりづらい。スクーリング申込みやレポート提出画面の使い勝手には、改善の余地を感じました。
Web上で授業や申込みが完結する仕組みは便利な反面、操作性やログイン制限の短さなどに不満を感じる声もあります。日々利用するシステムだからこそ、もう少し使いやすさを求める学生が多いようです。
卒業・就職・学習量
卒業率が公開されていません。通信制大学は卒業が大変と言われていますが、ライフスタイルと学びたいことのバランスを取りながら、時間をかけて学習する人も多いのでしょう。
— 在学生の口コミより通信教育部に在籍していますが、社会人を対象にしているように思えます。就職や進学に対する支援は皆無と言ってもいいです。
卒業までの道のりは長く、明確な統計が見えにくいことに不安を感じる人もいます。社会人向けの構成になっている一方で、就職や進学といったサポート面の薄さを指摘する声も見られます。
学び方・サポート体制
— 在学生の口コミよりすべてを丁寧に教えてもらえるわけではありません。大学なので、最後は自分次第です。学費や時間をかけるなら、その分しっかり吸収してやろうという気持ちで、自分でやる気を保つことが大切だと感じます。
通信制の特性上、受け身ではなく自ら学びを作っていく姿勢が必要とされています。サポートは最小限だからこそ、「どう学ぶか」を自分で設計できる人には向いている環境のようです。
気になる点・注意したい点(正直なメモ)
ここまで読むと「完璧なシステムでは?」と思うかもしれません。でも実際に通信で学ぶには、やっぱりそれなりの“難しさ”があります。口コミや情報を追っていく中で、気をつけておいた方がいいと感じた点をいくつかまとめます。
- モチベーションの維持が最大の壁
通信制は自由な分、すべての管理が自分にかかっています。レポート提出、課題制作、試験勉強——どれも誰かに催促されるわけではありません。「やるもやらないも自分次第」という環境は、社会人にとって両刃の剣。忙しい時期に後回しにしてしまい、そのまま続かなくなるという声も少なくありません。ペース配分を決めて、“小さくでも毎週手を動かす”のが大切になりそうです。 - 制作系コースは“環境づくり”が必要
美術やデザイン系の学科では、どうしても制作スペース・材料費・撮影環境が必要になります。オンラインで講評を受けられるのは便利ですが、「家でどこまで作業できるか」「どんな道具が要るか」は最初に考えておくべきポイントです。 - 人とのつながり方は“自分から”が基本
オンラインコミュニティ「airUコミュニティ」など、学生同士で交流できる場はありますが、通学のように自然に仲間ができるわけではありません。関わりを持ちたい人は、自分からSNSや展示会を通じてつながる姿勢が必要です。
逆にいえば、一人でじっくり向き合いたい人には心地よい距離感かもしれません。 - 「安い」とは言っても、それなりの投資
通信制は通学よりも学費が抑えられるのは確かですが、教材費・機材費・画材費など、意外と細かい出費が重なります。また、仕事をセーブして課題に取り組む時間を確保する人も多く、「お金よりも時間をどう確保するか」がリアルな課題になると思います。
まとめると、京都芸術大学の通信教育は「柔軟に学べるけれど、受け身では続かない学び」です。自由度の高さは魅力ですが、その分だけ“主体性”と“継続力”が問われます。
どんなにシステムが整っていても、最終的に動かすのは自分の手と意志。そこに向き合える人にとっては、間違いなく魅力的な環境だと思います。
まとめ
京都芸術大学の通信教育は、「社会人でも、きちんと芸術を学べる環境」を本気で作ろうとしている大学だと感じます。
オンライン中心の学びで、全国どこからでも挑戦できる一方、続けるには計画性と覚悟が必要。けれどその“自由と責任”のバランスが、社会人が通信制で学ぶ魅力でもあると思います。